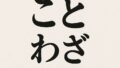弓道の距離の歴史と通し矢との関係とは

※本ページはプロモーションが含まれています
弓道を始めたばかりの方や興味を持った方にとって、まず気になるのが「弓道 距離」に関する基本知識ではないでしょうか。弓道には近的と遠的という競技があり、それぞれ異なる射距離が設定されています。この記事では、弓道の射距離は?という疑問から始まり、的までの距離はなぜ28メートルなのでしょうか?という歴史的な背景についても詳しく解説していきます。
さらに、江戸時代に行われた伝説の大会「三十三間堂の通し矢は何メートル先まで射たのですか?」というテーマにも触れ、当時の弓術と現代弓道のつながりをひも解きます。あわせて、競技を安全かつスムーズに進めるために欠かせない射場間隔は?という基本ルールについても整理してご紹介します。
初めて弓道に触れる方にもわかりやすく、弓道の距離にまつわる歴史と基礎知識をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
記事のポイント
-
弓道における近的と遠的の射距離の違い
-
近的競技の距離が28メートルに定められた理由
-
三十三間堂の通し矢と現代遠的競技の関係
-
射場間隔など競技時の安全ルール
弓道の距離に関する基本ルールを解説

-
弓道の射距離は?
-
的までの距離はなぜ28メートルなのでしょうか?
-
射場間隔は?
-
高校生の弓道競技における距離とは?
-
弓道の近的競技と遠的競技の違い
-
武徳会時代に決まった距離とは?
弓道の射距離は?
弓道における射距離は、競技の種類によって異なります。一般的に最もよく知られているのは、近的(きんてき)と呼ばれる競技で、これは28メートルの距離から的を狙います。一方、遠的(えんてき)と呼ばれる種目では、約60メートル離れた位置から直径1メートルの大きな的を狙うことになります。
このように言うと、非常に長い距離のように感じるかもしれませんが、弓道は単なる力比べではなく、精神の集中と正確な動作の積み重ねが重要な武道です。距離が長くなればなるほど、矢が空気抵抗を受けやすくなり、わずかな体のブレも命中率に大きく影響します。このため、弓道では正しい姿勢と動作が何よりも重視されています。
また、高校生の公式大会においても、近的競技は28メートル、遠的競技は60メートルで統一されており、全国共通のルールとして運用されています。これにより、どの地域の選手も同じ基準で競技を行うことができ、公平な試合が実現されています。
いずれにしても、弓道の射距離は単なる物理的な距離だけではなく、技術力や精神力の表れを試すための重要な要素であると言えるでしょう。
的までの距離はなぜ28メートルなのでしょうか?
近的競技において、的までの距離が28メートルと定められている理由には、歴史的な背景があります。これは単なる偶然ではなく、弓道の伝統と発展の過程で自然に決まったものです。
元々、日本の武士たちは戦の際に槍隊と弓隊を組み合わせて戦術を展開していました。このとき、槍隊と敵陣の距離を安全に確保しつつ、後方から弓隊が支援射撃を行うには、おおよそ十五間(約27.3メートル)が適していたとされています。これが、弓道の近的距離の原型と考えられています。
また、近代に入ると武徳会という武道団体が発足し、弓道の競技規則が整備されました。その中で、十五間半(約28メートル)という距離が標準化され、これがメートル法に換算された結果、現在の28メートルという距離が正式に採用されることになりました。
このような経緯から、28メートルという距離は単なる技術的な理由ではなく、武士の戦いの知恵と近代武道の制度化による歴史的な必然によって決まったものなのです。初めてこの話を聞く方にとっても、単なる数字以上に重みのある背景を感じていただけるのではないでしょうか。
射場間隔は?
弓道では、安全性と競技の円滑な進行を確保するために、射場間隔も厳密に定められています。ここで言う射場間隔とは、選手同士が弓を引く際の距離感や配置ルールのことを指します。
具体的には、選手同士の間隔は標準で1.8メートルとされ、場合によっては1.6メートルから2.0メートルの範囲で調整されます。また、射位(射つ位置)と本座(礼儀を行う位置)との間の距離は2.0メートルが標準とされています。さらに、選手落番(予備選手)の待機位置と後方の壁との距離は1.4メートル以上確保する必要があります。
このような細かな規定がある理由は、弓道が非常に大きな道具を扱う競技であり、かつ、繊細な動作が求められるためです。もし間隔が狭すぎれば、弓の動きが隣の選手と干渉してしまい、危険なだけでなく集中力にも悪影響を及ぼします。一方で、間隔が広すぎると競技進行に時間がかかりすぎ、試合運営が非効率になります。
つまり、射場間隔は、弓道の「安全」と「礼儀」を両立させるために、非常に重要な役割を果たしているのです。あなたがこれから弓道を始めるのであれば、単に「引く」ことだけでなく、こうした環境作りへの配慮も大切にしていただきたいと思います。
高校生の弓道競技における距離とは?
高校生が参加する弓道競技では、射距離が明確に定められています。近的競技では28メートル、遠的競技では60メートルが標準距離とされています。この規定は全国どこでも統一されており、すべての選手が同じ条件下で競技に臨むことができます。
現在の私は、高校弓道の大会では近的が最も多く実施されている印象を持っています。それは、学校に設置されている弓道場の多くが、28メートルの距離に合わせて設計されているためです。また、近的競技は天候に左右されにくく、安全面や運営面でも管理しやすいという利点があります。
一方、遠的競技は国民体育大会(国体)や遠的の全国選抜大会など、特別な大会でしか実施されない傾向にあります。このため、普段の練習環境で遠的専用の設備がない学校も多く、練習機会が限られるのが実情です。遠的では広いスペースが必要なうえ、風の影響も大きくなるため、より高度な技術と戦略が求められます。
こうして考えると、高校生にとっての弓道競技における距離設定は、単なる物理的な数字だけでなく、技術習得や大会運営の現実を踏まえた合理的な基準と言えるでしょう。
弓道の近的競技と遠的競技の違い
弓道には、近的競技と遠的競技という2つの主要な種目があります。それぞれに特徴があり、求められる技術や戦略も異なります。
まず近的競技は、28メートル先にある直径36センチメートルの小さな的を狙う競技です。室内や屋根付きの射場で行われることが多く、風や天候の影響をほとんど受けないのが特徴です。このため、選手の動作の正確さや集中力が勝敗を分けるポイントになります。
一方、遠的競技は60メートル先に設置された直径1メートルの的を射抜く競技です。屋外で行われることが一般的で、風の強さや方向、気温、湿度といった自然条件が成績に大きく影響します。このため、矢の飛び方を読む力や、臨機応変に射ち方を調整する柔軟性が求められます。
このような違いから、近的は「正確な動作の積み重ね」、遠的は「環境に適応する戦術」が問われる種目と言えるでしょう。あなたが弓道を学ぶのであれば、両方の競技に取り組むことで、より幅広い技術と精神力を磨くことができるはずです。
武徳会時代に決まった距離とは?
弓道の競技における距離が正式に定められたのは、武徳会時代のことです。武徳会とは、明治時代に設立された武道奨励団体で、近代日本の武道の体系化に大きな影響を与えました。
この武徳会によって、弓道の近的競技における標準距離が「十五間半」と決められました。十五間半とは、おおよそ28メートルに相当します。これをメートル法に換算した結果、現在の「28メートル」という規定が生まれたのです。
このとき、なぜ15間や16間ではなく15間半だったのかというと、戦国時代の戦術に由来するとされています。前述の通り、槍隊と弓隊が連携して戦った際、安全かつ効果的に支援射撃ができる距離が十五間半だったからです。つまり、武徳会は過去の戦術的経験を尊重しつつ、近代競技にふさわしい形で距離を整理したと考えられます。
こうして、武徳会時代に制定された28メートルの距離は、現在に至るまで日本全国の弓道場や大会で標準となっています。単純に数値だけを見ると無機質ですが、その背景には日本の武道文化の伝統と知恵が息づいているのです。
弓道の距離と歴史を三十三間堂の通し矢で知る

-
三十三間堂の通し矢は何メートル先まで射たのですか?
-
通し矢と遠的競技の距離の関係
-
江戸時代の弓道大会における距離
-
歴代通し矢記録とその難易度
-
近代弓道における距離の統一の流れ
-
現代の遠的大会で使用される距離について
三十三間堂の通し矢は何メートル先まで射たのですか?
三十三間堂の通し矢では、約120メートル離れた距離に向かって矢を放ちます。この距離は、現在行われている弓道の遠的競技(60メートル)よりもはるかに長く、当時の武士たちの高い技術と体力を示すものだったといえるでしょう。
このように言うと、120メートル先に矢を正確に射通すことがどれほど難しいか、想像できるかもしれません。実際、江戸時代に記録された最も優れた成績では、和佐大八郎という武士が一昼夜で13,053本の矢を放ち、そのうち8,133本を命中させたと伝えられています。この記録からも、当時の通し矢が単なる競技ではなく、極限まで集中力と体力を研ぎ澄ませる武道的修行であったことがわかります。
さらに、三十三間堂の通し矢は単に的を狙うだけではなく、本堂の長い軒下を矢が通過すること自体を目的とするものでした。そのため、精度だけでなく、矢の軌道や飛距離のコントロールも極めて重要だったのです。今でも、毎年1月に開催される「大的大会」では、新成人が約60メートル先の的を狙って競技を行っていますが、これはかつての伝統を現代に伝える重要な行事となっています。
通し矢と遠的競技の距離の関係
通し矢と現代の遠的競技は、距離や目的において共通点と違いを持っています。共通しているのは、いずれも通常の近的よりもはるかに遠い距離から的を狙う点です。しかし、細かなルールや競技の趣旨は大きく異なります。
まず、通し矢では三十三間堂の約120メートルという非常に長い距離を、矢が本堂の軒下を通過する形で射ることが目的でした。ここでは、一昼夜かけて何本射通せるか、つまり「量」と「耐久力」が重視されていました。一方、現代の遠的競技では、60メートル先の直径1メートルの的に対して命中させる「正確性」が求められます。競技時間も限られており、技術だけでなく、短時間で結果を出す力が試されます。
こうして比較してみると、通し矢は持久戦に近い性質を持ち、遠的競技は短期集中型の試合形式であることがわかります。また、遠的では得点制を採用する大会もあり、ただ当たるだけでなく、より中心に近い場所を射抜くことが高得点につながる仕組みです。
このように考えると、通し矢と遠的はともに弓道の「遠距離射撃」の伝統を受け継いでいながら、それぞれ時代に応じた競技形式へと発展してきたことが理解できるでしょう。
江戸時代の弓道大会における距離
江戸時代の弓道大会では、現在の競技とは異なり、距離設定にもさまざまな特徴がありました。特に有名なのが、三十三間堂で行われた通し矢です。この大会では、120メートルという長大な距離を矢が通過するかどうかを競い、武士たちの間で名誉と技術力の証明として高いステータスを誇っていました。
一方、城下町や各藩で行われていた一般的な弓術大会では、もっと短い距離が採用されることもありました。例えば、十五間(約27メートル)や十六間半(約30メートル)といった距離が標準とされる場合があり、これらは地域や流派によって若干の違いが見られました。これは、使用する弓の種類や、武士たちの鍛錬目的によって最適な距離が選ばれていたためです。
このように、江戸時代の弓道大会における距離設定は、単に技術の競い合いにとどまらず、各藩の誇りや文化の違いを色濃く反映していました。多くの場合、藩の威信をかけた真剣な勝負であり、単なる娯楽ではなかったことを理解しておく必要があります。
こうして振り返ると、現代弓道の競技規則が統一されていることは、当時と比べると大きな進歩といえるでしょう。今でも弓道が「礼に始まり礼に終わる」とされる所以は、こうした長い歴史と武士たちの精神文化に根ざしているのです。
歴代通し矢記録とその難易度
通し矢は、三十三間堂の約120メートルという長い距離を射通す競技であり、その記録には驚くべきものがあります。中でも最も有名なのは、紀州藩の和佐大八郎が打ち立てた記録です。彼は貞享3年(1686年)、一昼夜の間に13,053本の矢を放ち、そのうち8,133本を軒下に通しました。この命中率は約62%にも及び、現在でも破られていない伝説的な記録とされています。
このような記録を聞くと、単なる腕力だけでは達成できないことがわかります。120メートル先に向けて矢を連続して放つには、精密な射術に加え、途切れることのない集中力、強靭な体力、そして持久力が必要です。しかも、三十三間堂の軒下を貫くためには、単に的を狙うのではなく、矢の高さと角度を正確にコントロールしなければなりません。
さらに、当時の弓具は現代ほど精巧ではなかったため、今以上に射手の技術が問われたことも忘れてはいけません。例えば、気温や湿度による弓の変形、矢の飛び方の微妙なズレなども、射手自身がその場で読み取って対応していたのです。
このように、歴代通し矢の記録は単なる数字の羅列ではなく、当時の弓術家たちが持っていた驚異的な能力と、武道精神の高さを物語るものなのです。
近代弓道における距離の統一の流れ
近代弓道では、競技の標準距離を全国で統一する動きが進められました。この流れは、明治時代に設立された武徳会が中心となって整備されていきます。
それ以前の日本では、地域や流派によって競技距離にばらつきがありました。関東地方では16間半(約30メートル)、関西地方では13間半(約24メートル)など、場所によって基準が異なっていたのです。しかし、武道を国民教育の一環と位置付ける流れの中で、弓道もまた統一されたルールを必要とするようになりました。
ここで武徳会が設定したのが、十五間半、すなわち約28メートルという距離です。この距離は、古くから戦場で槍隊と弓隊が共に行動する際の実践的な間合いに基づいており、単なる机上の数字ではありませんでした。また、メートル法導入後もこの伝統を尊重し、28メートルとして正式に統一されることになります。
このため、現代の弓道では全国どこの道場でも28メートルが基本距離となっており、初めて弓道に触れる人でも迷うことがありません。競技の公平性や練習環境の整備にも大きく貢献した、非常に意義深い決定だったと言えるでしょう。
現代の遠的大会で使用される距離について
現代の弓道において、遠的大会では基本的に60メートルの距離が使用されます。この60メートルという設定は、単なる目安ではなく、伝統と競技性のバランスを考えた結果、正式に定められたものです。
例えば、全日本遠的選手権大会や国民体育大会(国体)の遠的競技では、60メートルの射距離が採用されています。この距離は、近的競技の28メートルとは異なり、風の影響を強く受けるため、単に正確な射技だけでは対応できない場面も多々あります。選手は風向きや強さを瞬時に判断し、それに合わせた射を行わなければならないため、技術と経験の総合力が求められます。
また、遠的では使用する的も近的とは異なり、直径1メートルの大きな的が用いられます。これにより、遠距離からでも的を捉えやすくなっていますが、中心を狙う精度を求められる点では難易度が高いままです。さらに、遠的では的中数だけでなく、矢の着地点による得点制を採用する大会もあり、戦略的な射ち分けが勝敗を左右するケースもあります。
このように考えると、現代の遠的競技は単なる「遠くに射る」だけではなく、高度な読みと技術の応酬で成り立っている奥深い競技だとわかります。初めて挑戦する方にとっては難しく感じるかもしれませんが、その分達成感も大きなものとなるでしょう。
弓道の距離に関する基本と歴史をまとめて解説
-
弓道の射距離は競技によって異なる
-
近的競技では28メートルの距離を用いる
-
遠的競技では60メートル先の的を狙う
-
的までの距離が28メートルなのは武士の戦術に由来する
-
近代に武徳会が距離を15間半(約28m)に統一した
-
射場間隔は標準1.8メートルで安全を確保する
-
高校生の弓道大会も28メートルと60メートルに統一されている
-
近的競技は正確な動作を重視する競技である
-
遠的競技は風など自然条件に対応する力が必要である
-
三十三間堂の通し矢は約120メートルの距離を射抜く競技だった
-
通し矢は持久力と集中力が問われる過酷な競技だった
-
現代の遠的競技は的中率と得点が勝敗を分ける
-
江戸時代の弓道大会では地域ごとに距離設定が異なっていた
-
歴代通し矢記録は驚異的な命中率を誇る
-
現在の遠的大会は60メートルを標準距離として実施されている
関連記事:弓道とアーチェリーの違いとは?道具と文化の差を解説
人気記事:弓道の安土の基礎知識と整備方法を徹底解説