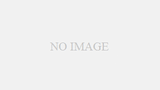弓道の「もたれ」とは?原因と克服法を徹底解説

※本ページはプロモーションが含まれています
弓道を続けていると、誰しも一度は「もたれ」という壁に直面することがあります。もたれとは、会の状態で離れが出せなくなり、弓を引いたまま動作が止まってしまう現象です。これは単なる技術的なミスではなく、心と体のバランスが崩れることによって生じる複雑な課題です。
「もたれ・びくの原因が知りたい」「もたれは何秒から起きるのか?」といった疑問を持つ方に向けて、本記事では、もたれの正体や原因、そして改善のための具体的な対策をわかりやすく解説していきます。
もたれはつらいと感じるのは、単に矢が放てないという問題だけでなく、自信の喪失や精神的な重圧を伴うためです。しかし、正しい知識と練習方法を身につければ、必ず克服することができます。
この記事では、もたれの治し方を中心に、原因や対策、日常のトレーニング法まで網羅的に紹介していきます。弓道に取り組むすべての射手が、心地よい会と自然な離れを取り戻せるよう、実践的なヒントをお届けします。
記事のポイント
-
もたれとは何か、その基本的な意味と現象
-
もたれ・びくが起こる主な原因とメカニズム
-
もたれは何秒から起きやすいかという目安
-
もたれを克服するための具体的な練習法と考え方
弓道のもたれとは何か?基本を解説

-
もたれとはどんな現象なのか
-
もたれ・びくの原因を正しく理解する
-
もたれは何秒から起きるのか
-
もたれはつらいと感じる理由
-
もたれと「はやけ」の違いとは
もたれとはどんな現象なのか
もたれとは、弓道において「会(かい)」の段階で矢を放てず、弓を引いたまま動作が止まってしまう現象のことを指します。特に離れのタイミングを失い、必要以上に長く引き続けてしまう状態を言います。これは単なるタイミングのズレではなく、精神的・身体的な要因が複雑に絡み合って発生するため、多くの射手にとって克服が難しい課題の一つです。
例えば、会に入ったものの矢を放つ自信が持てず、数秒以上も弓を引いたまま固まってしまうケースがあります。この状態が続くと、肩や腕の筋肉に無駄な力が入り、射形が崩れる原因となります。また、精神的にも「いつ離れを出せばいいのか分からない」と不安が増し、さらに緊張が高まる悪循環に陥ることがあります。
言い換えれば、もたれは弓道における「動作の停滞」であり、無理に離れを出そうとすれば「びく(震え)」などの別の問題も引き起こしかねません。このような状態を防ぐためには、単に技術を磨くだけでなく、自分自身の心と体の状態に向き合い、安定した射を目指すことが重要です。
つまり、もたれは一時的な技術ミスではなく、射手の内面や射形に深く関係する現象であるため、根本的な見直しと継続的な練習が必要となります。
もたれ・びくの原因を正しく理解する
もたれやびくが起こる背景には、精神的な要素と身体的な要素の両方が関係しています。これを正しく理解することで、自分の射を見直すきっかけとなり、改善への第一歩を踏み出すことができます。
まず精神的な原因としては、離れに対する過剰な意識や不安が挙げられます。多くの場合、「的を外したくない」「失敗したらどうしよう」という気持ちが強くなりすぎて、矢を放つタイミングを逃してしまいます。この不安が強くなると、体がこわばり、自然な動作ができなくなります。その結果、もたれやびくといった問題が表面化するのです。
一方、身体的な要因では、力みや筋力不足が挙げられます。特に肩や腕の筋肉が緊張している状態では、会を安定して保つことが難しくなります。また、射形が乱れていたり、弓の押しが弱かったりすると、弓を引ききった後に体がブレやすくなり、びくが起こりやすくなります。
例えば、引分けの際に腕だけで弓を引こうとすると、全身の連動がうまくいかず、会に入った瞬間に余計な力が集中してしまいます。このとき、呼吸が浅くなると、精神面でも不安が強まり、離れを出せずにもたれるという結果になります。
このように、もたれやびくの原因は一つではなく、複数の要素が絡み合っています。そのため、症状を根本から改善するためには、技術面だけでなく心身のバランスを意識することが不可欠です。
もたれは何秒から起きるのか
もたれが起こる時間には個人差がありますが、一般的には会の状態が7~8秒を超えると、体と心に負担がかかり始めると言われています。特に10秒を超えると筋肉がこわばりやすくなり、離れが出しにくくなる傾向があります。
本来、会の時間は安定した呼吸とともに、落ち着いて矢所を見定めるための重要な段階です。しかし、長く引き続けることで、次第に腕や肩に余計な力が入り、体全体のバランスが崩れてしまいます。すると、矢を放つタイミングを失い、もたれの状態に陥ってしまうのです。
具体的には、5〜6秒程度で自然に離れが出せるようになると、筋肉や精神に無理なく動作を進めることができます。これに対して、8秒を超えると「そろそろ離さなければ」という焦りやプレッシャーが生まれやすくなり、その心理的負担がさらに離れを妨げる要因となります。
もちろん、個人の体力や経験、弓力によって最適な時間は異なります。ただし「長く持つことが正しい」と考えて無理に会を保とうとするのは逆効果です。安定した射形を維持しつつ、自然なタイミングで離れを出せるよう練習を重ねることが、もたれを防ぐ鍵となります。
つまり、時間だけにとらわれるのではなく、自分の状態をよく観察しながら、最も自然で無理のないタイミングを見つけることが大切です。
もたれはつらいと感じる理由

もたれを経験する射手の多くが「つらい」と感じるのは、単なる技術的な問題にとどまらず、精神的な負担が非常に大きいためです。弓を引いたまま離れが出せない状態は、体力的な限界だけでなく、自信の喪失や焦りなど、メンタルへのダメージを伴います。
特に試合や昇段審査といった緊張感の高い場面では、「今、離さなければいけない」と自分にプレッシャーをかけすぎてしまい、かえって離れを出すタイミングを失います。その結果、「なぜ自分だけうまくいかないのか」と自分を責めてしまい、弓道そのものが苦しく感じるようになるケースも少なくありません。
また、もたれは一度起きてしまうと、次の射でも再発するのではないかという不安が残ります。この「またもたれたらどうしよう」という恐怖心が積み重なると、会の時間がますます長くなり、悪循環に陥ってしまうのです。こうした精神的なスパイラルは、身体的な疲労よりも深刻な問題を引き起こします。
さらに、周囲の目を気にしてしまう人ほど、もたれを「恥ずかしい失敗」と感じやすくなります。弓道では静寂の中で一人が的に向かうため、自分の動作が他人に注目されやすいという特性があります。そのため、会で止まったまま動けなくなると、他の射手や審査員からどう見られているかが気になり、余計に心が締めつけられるのです。
こうした状況が続くことで、弓道に対して前向きになれなくなったり、練習を避けてしまう人もいます。このように、もたれは肉体以上に心に重くのしかかる現象であり、多くの射手にとって「つらい」と感じるのは、ごく自然な反応と言えるでしょう。
もたれと「はやけ」の違いとは
弓道における「もたれ」と「はやけ」は、どちらも離れに関する問題ですが、起きている現象や原因はまったく異なります。これらの違いを正確に理解することが、改善に向けた大切な第一歩となります。
「はやけ」は、会に入る前、あるいは狙いが定まる前に無意識に離れてしまう現象を指します。つまり、本来のタイミングよりも早く矢を放ってしまうのが特徴です。この背景には、「早く射なければならない」という焦りや、体の緊張、習慣化した癖などが関係しています。特に初心者や緊張しやすい人に多く見られます。
一方、「もたれ」はその逆で、矢を放つことができず、弓を引いたまま動作が止まってしまう現象です。会に入った後、「離れのタイミングがわからない」「怖くて離せない」といった精神的な迷いが原因で、身体が固まり離れが出せなくなります。見た目は静かに見えるかもしれませんが、射手の内面では強い葛藤が起きている状態です。
両者の違いを簡単にまとめると、「はやけ」は「早すぎる離れ」、「もたれ」は「遅すぎる離れ」と言えます。しかし単純に時間の問題だけではなく、精神的な反応の方向性が真逆である点にも注目すべきです。前者は反射的、後者は抑制的な反応と言えるでしょう。
このように、似ているようで全く異なる「もたれ」と「はやけ」ですが、どちらも弓道における重要な課題です。自分がどちらの傾向にあるのかを見極め、それぞれに応じた対策を取ることが、安定した射につながっていきます。
弓道のもたれの対策と改善方法

-
もたれの治し方と練習の工夫
-
精神的プレッシャーとその対処法
-
ゆすりを抑える正しい弓の引き方
-
緩み離れを防ぐ意識と動作の整え方
-
メンタル面からもたれを克服する方法
-
日常でできるもたれ予防トレーニング
-
離れの感覚を養うための練習方法
もたれの治し方と練習の工夫
もたれを改善するには、射の技術だけでなく、意識の持ち方や練習内容にも工夫が必要です。単に「早く離れを出そう」と意識するのではなく、体と心のバランスを整えるアプローチが効果的です。
まず重要なのは、「押し」を意識した射を習慣づけることです。もたれが起きると、どうしても「離れをどう出すか」に気を取られてしまい、引く動作ばかりに集中してしまいがちです。そこで、逆に「押しの力を最後まで継続させる」ことを意識すると、結果として自然な離れにつながります。押しと引きの均衡が取れていれば、会の状態も安定し、無理のないタイミングで矢が離れるようになります。
次に、会の時間をコントロールする練習も有効です。例えば、ストップウォッチを使って7〜8秒で離れを出す練習を繰り返すことで、体にリズムが染みついていきます。最初は3〜5秒の短い会から始め、段階的に時間を延ばしていくと、精神的な負担を軽減しつつタイミングの感覚を養えます。
また、「目隠し射法」や「巻藁射」での意識練習もおすすめです。目を閉じて射の流れを感じ取ることで、余計な視覚情報からのプレッシャーを減らし、自分の身体感覚に集中できます。巻藁で繰り返し正しい離れの感覚を磨いておけば、的前でも自然に離れるようになります。
いずれにしても、「離れを出さねば」と考えるほど体が固まりやすくなります。押し・呼吸・リズムの3点を意識し、自然に動作が流れるような練習を積み重ねていくことが、もたれを克服するための大切な一歩となるでしょう。
精神的プレッシャーとその対処法
もたれの原因の多くは、精神的なプレッシャーに由来します。特に試合や昇段審査など、結果が求められる場面では「失敗したらどうしよう」という不安から体が硬直し、離れが出せなくなります。そこで、精神面へのアプローチは技術的対策と同じくらい重要です。
まず行ってほしいのは、離れへの意識を軽くすることです。「離れを出さなければ」と思い詰めるほど、その動作が特別なものに感じられてしまい、体が自然に動かなくなります。むしろ、離れは「押しの継続によって結果的に起こる動作」と捉えることで、精神的な負担を減らせます。
次に、呼吸の見直しも有効です。精神的な緊張が高まると呼吸が浅くなり、体に余計な力が入ります。深く、ゆったりとした呼吸を繰り返すことで心拍が安定し、リラックスした状態を作り出すことができます。特に会に入ってからの呼吸に注意を向けると、自然に動作へと移れるようになります。
加えて、ポジティブなイメージトレーニングも効果的です。射を始める前に、自分が落ち着いて矢を放つ姿を頭の中で描いてみてください。成功のイメージを繰り返し刷り込むことで、実際の場面でも安心感を持って動作に臨めるようになります。
もし練習中にプレッシャーが強くなってきたら、一旦射を中断する勇気も大切です。無理に続けて悪い癖を染みつかせるよりも、心身の状態を整えてから再開したほうが、結果的に上達につながります。精神的な安定は、一朝一夕で手に入るものではありませんが、日々の練習の中で意識することで徐々に身についていくものです。
ゆすりを抑える正しい弓の引き方
ゆすりとは、会の状態で弓や腕が細かく震えてしまう現象で、狙いが安定しなくなるため的中率にも影響を及ぼします。このゆすりを抑えるには、正しい姿勢と力の配分を意識した弓の引き方を身につける必要があります。
まず、基本となるのが「骨格で支える」姿勢を取ることです。腕や肩の筋力だけで弓を支えようとすると、体が早く疲れ、震えが生じやすくなります。足踏みから胴造りまで、骨格に無理のない形で構えることで、長く安定して会を維持することが可能になります。特に腰の位置が重要で、重心を下げて安定感を持たせると、上半身にかかる負担が軽減されます。
次に、「押しと引きのバランス」にも注意が必要です。片方の腕だけで弓を操作していると、力の偏りから弓が揺れやすくなります。両腕でしっかりと均等に張り合いを作ることで、弓全体にかかる力が安定し、ゆすりが起きにくくなります。
また、会の状態での呼吸も見直しましょう。呼吸が浅くなると筋肉が緊張し、微細な震えが起こりやすくなります。会に入っても呼吸を止めず、一定のリズムで空気を取り入れ続けることで、体の余計な力みを防げます。
もしすでにゆすりが出てしまう場合は、あえて「短い会」を繰り返す練習を取り入れるとよいでしょう。5秒以内で離れを出すことで震えが起きる前に動作を完了できるため、射のリズムを整える助けになります。
このように、正しい姿勢・力の配分・呼吸のリズムを意識した弓の引き方を心がければ、ゆすりを大きく軽減することが可能になります。安定した会は、結果として射の全体的な質の向上にもつながります。
緩み離れを防ぐ意識と動作の整え方
緩み離れとは、会の状態が不安定なまま離れを出してしまうことで、矢の勢いや狙いに乱れが生じる現象です。この問題を解決するには、射の意識の持ち方と動作の精度を見直すことが不可欠です。
まず、会の段階で「張りを維持する」意識が重要です。弓を引ききった瞬間に気持ちが緩むと、それが体にも伝わり、押しの力が抜けてしまいます。このような状態では、離れを出した際に力の伝達が不十分になり、矢勢のない不安定な射になってしまいます。そこで、「離れは押しの延長線上にある動作」と考えるようにしましょう。力を抜くのではなく、押しを継続している中で自然に弦が切れるような感覚を養うことが大切です。
次に、射のリズムを一定に保つ練習が効果的です。毎回異なる会の時間では、体がどのタイミングで動けばよいか迷いやすくなります。7〜8秒程度を目安に、決まったテンポで動作を行うことで、会の張りを安定させやすくなります。この際、鏡の前で自分の姿勢をチェックすることで、客観的に形の乱れにも気づけるようになります。
また、的中に執着しすぎないこともポイントです。的を意識するあまり、離れのタイミングに余計な緊張が加わると、押しや張りが弱まり、緩み離れの原因となります。練習では、あえて的を外して「動作の完成度」を重視する射を繰り返すと、精神的な余裕も生まれ、離れに安定感が出てきます。
つまり、緩み離れを防ぐには、押しを中心に意識を持ち、射のリズムを整え、形に集中する姿勢が求められます。無理に力を抜かず、自然な流れで離れが出るようにすることが、安定した射形への近道です。
メンタル面からもたれを克服する方法

もたれが続くと、「離れが出せない自分」に対する不安が大きくなり、弓道そのものが苦痛に感じてしまうことがあります。そのような負のスパイラルに陥らないためにも、メンタル面からのアプローチが欠かせません。
まず大切なのは、「離れに対する意識を変える」ことです。多くの射手が、離れを特別な動作として捉え、「絶対に失敗してはいけない」という考えに縛られてしまいます。このような意識はプレッシャーを増幅させ、体が動かなくなる原因になります。そこで、離れを「押しの動作の結果として自然に出るもの」と再定義し、離れを目的化しないことが重要です。
加えて、深呼吸やマインドフルネスを取り入れるのも効果的です。例えば、射を始める前に3回深く息を吸って吐くだけでも、心の落ち着きが生まれます。さらに、会に入った後も呼吸を止めずにゆったりとしたリズムを保つことで、体が自然とリラックスした状態になります。このような呼吸の工夫は、精神的な緊張を和らげ、もたれの発生を防ぎやすくします。
また、成功体験を意識的に思い出すことも役立ちます。過去にうまく射てた時の自分の感覚や姿勢を何度も頭の中で再生し、そのイメージに沿って行動するようにすると、安心感と自信が生まれます。加えて、「今回はうまくいかなくても大丈夫」という柔軟な気持ちも持つことで、結果に縛られず、のびのびと射に臨めるようになります。
このように、もたれを克服するには、「離れを気にしすぎない」「呼吸で心を整える」「成功のイメージを繰り返す」といった意識づけが効果を発揮します。精神の安定が、射の安定にも直結するということを忘れずに取り組んでみてください。
日常でできるもたれ予防トレーニング
もたれを防ぐためには、弓道の稽古場以外でも取り組める日常的なトレーニングが重要になります。特に、精神的な安定と身体の柔軟性を高めることは、射の中での余計な緊張を取り除くうえで大きな助けになります。
まず意識したいのは、姿勢を保つための体幹トレーニングです。弓を安定して引くためには、腕や肩だけでなく、全身のバランスが必要になります。特に腹筋や背筋を中心とした体幹を鍛えることで、会の姿勢が安定し、無駄な力みが減少します。自宅でも行えるプランクやスクワットなどの簡単な筋力トレーニングを、無理のない範囲で継続していくとよいでしょう。
加えて、柔軟性を高めるストレッチも欠かせません。肩甲骨周辺の可動域が狭いと、引き分けから会にかけての動作がぎこちなくなり、結果として力みやもたれにつながります。日常的に肩回りや背中、胸の筋肉をほぐすようなストレッチを取り入れることで、弓を引く際の可動域が広がり、自然な射がしやすくなります。
さらに、呼吸を整える習慣もメンタル面の安定に寄与します。深い腹式呼吸を意識することで、自律神経が整い、緊張しやすい場面でも落ち着いて射に臨むことができます。例えば、朝起きたときや寝る前に、静かな場所でゆったりとした呼吸に集中する時間を数分間作るだけでも効果があります。
このように、日常生活の中で無理なく取り入れられるトレーニングを継続することで、もたれを引き起こす要因を一つひとつ減らすことができます。意識的な体づくりとメンタルケアが、安定した射を支える土台となるのです。
離れの感覚を養うための練習方法
離れの感覚を正しく身につけることは、もたれの克服にも直結します。離れは弓道の中でも最も難しい動作の一つとされており、そのタイミングや感覚は体で覚える必要があります。ここでは、感覚を磨くために効果的な練習法をご紹介します。
最初に取り入れやすいのが、「目隠し射法」です。これは文字通り、目を閉じた状態で弓を引き、会の形を感じながら離れを行う方法です。視覚情報がないぶん、身体の感覚に意識が集中しやすく、離れの自然なタイミングを体に覚えさせることができます。ただし、安全面に配慮し、巻藁などを使った静的な練習に限って行うようにしてください。
もう一つは、「呼吸と動作を連動させる練習」です。これは、会に入ってから呼吸のリズムに合わせて離れを出すというものです。例えば、深く吸って、ゆっくり吐きながら離れを迎えるようなリズムを意識することで、自然と身体の力みが抜け、無理のない離れができるようになります。この方法は、緊張をやわらげ、精神的な負荷も軽減する効果があります。
さらに、鏡を使ったフォームチェックも有効です。自分では正しく動作しているつもりでも、実際には力みやバランスの崩れが生じていることがあります。鏡を見ながら、離れまでの一連の流れを繰り返し確認することで、動作の安定性が向上し、離れの感覚もよりクリアになります。
このように、視覚・感覚・呼吸といった複数の要素にアプローチする練習を行うことで、離れを「考えるもの」から「感じるもの」へと変えていくことができます。繰り返し丁寧に練習を重ねることで、もたれを引き起こさない自然な離れを習得することができるでしょう。
関連記事:弓道のはやけが起こる理由とは?原因と効果的な改善法を解説
人気記事:安土整備のやり方を基礎から丁寧に解説